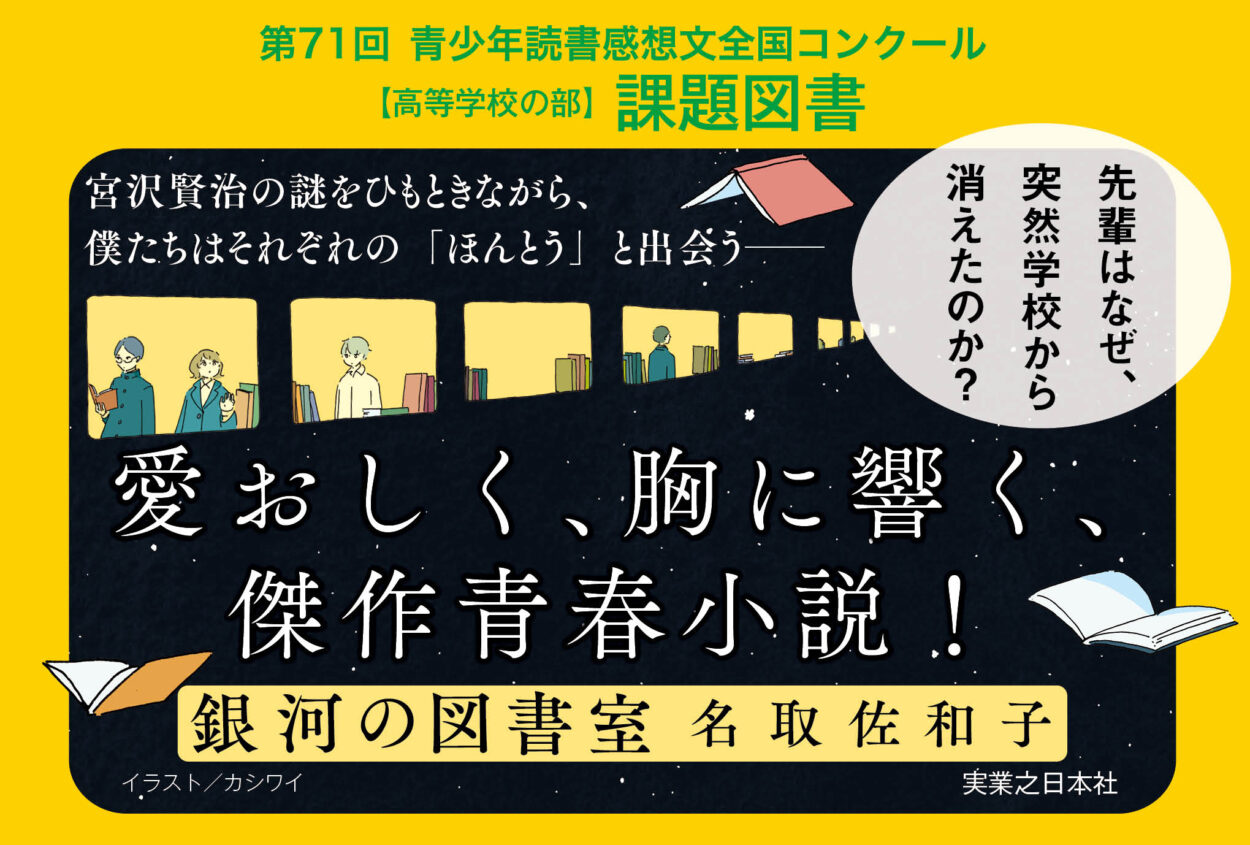堂場瞬一氏
1963年生まれ。茨城県出身。2000年秋『8年』にて第13回小説すばる新人賞を受賞。主な著書に「刑事・鳴沢了」シリーズ、「警視庁失踪課・高城賢吾」シリーズなどの警察小説の他、スポーツ小説も多数執筆。スポーツ小説最新刊は文庫化された『ラストダンス』(実業之日本社)。

NET21ブックスページワン赤羽店 清宮久雄さん

リブロ池袋本店マネージャー 昼間 匠さん
堂場瞬一とカリスマ書店員が語る「スポーツ小説」の魅力
2012.08.16
スポーツ小説というジャンル
……堂場さんは、“スポーツ小説”を書いているという意識なのでしょうか。
堂場: そもそもスポーツ小説というジャンルがあるのか、議論の余地がありますが(笑)、何よりも作家としてスポーツには魅力を感じています。ただ、他の作家さんのスポーツものは、若い人の成長譚が多い。自分はオヤジなので、年齢に関係なく読めるスポーツ小説を書きたい気持ちがあるのです。
昼間: リブロ池袋店では男性のお客様が多く、野球やサッカーのような、かつて読者たちがやっていたであろうスポーツが読まれている印象です。
清宮: スポーツ小説と聞くと、そのスポーツへの興味や知識が必要だろうと思われている節もあります。実際はスポーツを通した人間ドラマを見ているんですけれど。
堂場: その匙加減はいつも考えていて、プレーそのものを詳しく書けば書くほど、知らない人は読みにくくなる。かといって競技を添え物にして人間ドラマに注力しすぎると、本来書きたいものとは違ってきてしまう。その塩梅はいつも悩みの種です。
昼間: 難しいところですよね。そのスポーツのファンが読めばちゃんと書けていないと言われそうですし、逆に普通の人には難しくてわからないとも言われてしまいそうです。
イヤなやつへの共感 堂場瞬一の着眼点
……堂場さんのスポーツ小説の魅力はどこにあると思いますか?
昼間: 堂場さんの作品は、マラソンのペースメーカーや水泳のメドレーリレー、引退間際の野球選手のような斜めの題材が多いですよね。
堂場: 自分ではど真ん中のつもりです(笑)。一つ考えているのは、若い選手より、頂点から下り坂の選手の方が、人間味が出てくる。果実は、熟し切って枝から落ちる直前がうまいんですね。スポーツ選手は経験を積めば積むだけ味が出てきますから、それを表現したい。先程も言いましたが、若者の成長譚を書かれる方はたくさんいて、代表作があさのあつこさんの『バッテリー』なわけです。あれはスポーツ小説のひとつの基準になっていると思います。子どもが成長していく、青春の物語。ただぼくは、子どもを書くのが好きではない。それで、オヤジたちが読むに耐えうるのは中学生や高校生ではなく、引退間際のおっさんたちの物語だろうと。
昼間: はい、わたしもそこが魅力だと思っています。堂場さんにとってはストレートかもしれないけれど、読者には変化球的な題材を、皆さんおもしろがって読んでいると思います。
堂場: そうすると、ぼくの感覚がズレていると…
一同: (笑)
昼間: いい意味での外しと捉えています(笑)。わたしは堂場作品のなかで『チーム』がいちばん好きなのですが、主人公が箱根駅伝の学連選抜チームというのは驚かされました。読んでから箱根駅伝を観ると、それまで何気なく見ていた学連選抜に思わずいろいろな想像を巡らせてしまいます。自分のスポーツ経験を通した共感はもちろんですが、若い頃は頑張る姿に感動していたのが、社会人になり年をとるとチームと選手の関係が、会社と社員のようなテーマとしても読める。
堂場: 年を重ねると、傲慢キャラやヒール役に対する見方が変わってきます。若い頃は嫌なやつだと思っていたのが、大人になると理解できるようになる。
清宮: わたしは部活でのスポーツの経験がまったくないので、競技者としての共感はあまりありません。観戦は好きでよくするのですが、いわゆるスポーツ観戦は試合だけを観るものですよね。でも小説は試合だけじゃなくて、そこに至るまでの過程にスポットが当たる。それはスポーツ小説ならではのおもしろさだと思うんです。それならドキュメンタリーもあるじゃないかと言われますが、映像にはアスリートの本音が出ているとは限りません。嘘を言っているということではなく、選手たちにもTVであるという前提があるわけで、本当に本当のところは見えてこない。ですが、小説はフィクションだけれど、もしくはフィクションであるがゆえに必要なことがすべて描かれますよね。
堂場: たしかにドキュメンタリーだからといって、選手たちの言葉がすべて本音ではないと思います。当然、取材側の編集も入りますしね。
……そういう意味でも、スポーツ小説のリアルとは何なのかという話も出てきそうです。
堂場: 「共感」には、「うれしい」や「悲しい」だけではなく、「こいつ嫌な奴だけど、気持ちはわかる」というのもあるわけで、そこをリアルに感じてもらえたらうれしい。たとえ同じスポーツをやっていた人でも、Aという人とBという人ではプレーに対する取り組み方も考えも全然違います。だから万人が納得できるような心理描写はできないし、ないんです。スポーツ上級者の世界はかなり特殊なので、普段は表に出てこない世界を、少しでも読者に提示したいという思いがあります。
スポーツ小説=スポーツ観戦
清宮: わたしがいちばん好きなのは、オリンピック水泳のメドレーリレーを描いた『水を打つ』です。上下巻で800ページでしたが、二日で一気に読みました。臨場感がすごくて、登場人物たちがまるで目の前にいるようでした。そういう読書体験をみなさんにも味わってもらいたいですね。
堂場: 特に今年の夏にはピッタリですね。ナショナルチームは、普段顔を合わせない人たちが一緒にやるわけで、『チーム』と似た状況ですよね。年齢も背景も全く違う人たちが味方として集まったけれど、本来はライバルでもあるという、微妙で複雑な関係を描き易いモチーフでもありました。
清宮: 今岡というベテラン選手は、期待のニューフェイスに「まだやるんですか」と言われたりしてとても切なかった。アスリートの人にとって、引き際を決めることはとても難しいことなのだろうなと感じました。『ラストダンス』の主役二人は、まさにそういう引退直前という状況のお話でしたね。
……どの作品にも必ずヒールキャラがいます。最初にこいつがヒール、と立てていくものなんですか?
堂場: そうですね、比較的立てるほうだと思います。
……堂場さんが思い入れのあるキャラクターは?
堂場: やっぱり『チーム』とその続編『ヒート』に出てくる山城です。ヒールの典型ですよね。改心したかと思えば、やっぱりそうでもないという。人間としてはだめなやつ。でも、トップを行こうとする気持ちが強ければ強いほど、ある程度わがままになるということはあると思います。僕が描きたいのは成長物語じゃない、というのはそういうことです。スポーツをやっていると、どうしても嫌な人間になってしまうこともあるよというのが、僕なりのリアルだと思っています。そもそも誰かに勝ちたいという気持ちは、自然なエゴではないでしょうか。
昼間: いま、清宮さんも言われた引退間際の選手二人を描いた『ラストダンス』は、結末に驚かされました。最後はどうなる? とハラハラしながら読んで、そう来たか! という感じ。
堂場: スポーツは事前に結果がわからない。同じ感覚を小説で感じてもらえていたら、うまくいったということですね。最近マイナースポーツとは何かみたいなことをよく考えるんですが、本来マイナーなスポーツなんてものはひとつもないはずで、注目されているかいないかだけの違いなんだと思います。まず試合を見てもらうことで認知されるわけで、ぼくの本を読んだ後には、生の試合をぜひ観てみてほしい。小説を読むことは、実際に試合を見ることと似ていると思うんです。そのきっかけになってくれたら、これ以上ない喜びですね。
スポーツ小説の売りどきのヒミツ
……ちなみに書店では、オリンピックやWBC、W杯のようなイベントがあると本が売れるものですか?
昼間: 試合の結果によりますよね。オリンピックコーナーは作るけれども、開催中に売れるかというとそうでもない(笑)。たしかに本はたくさん出るんです。書店としては結果がどうなるのかわからないけど、本自体は取っておかないと突然無名の選手が勝ったりして、急に本が売れてしまったりします。そうすると出版社に在庫がないということも起こってしまうので、先にフェアを組んでおくんです。
堂場: そうすると我々は今まで、発売戦略を間違っていたのかもしれない(笑)。よし、今後のやり方を考えなおそう。
※本特集は読売新聞2012年8月18日に掲載された座談会のロングバージョンです。