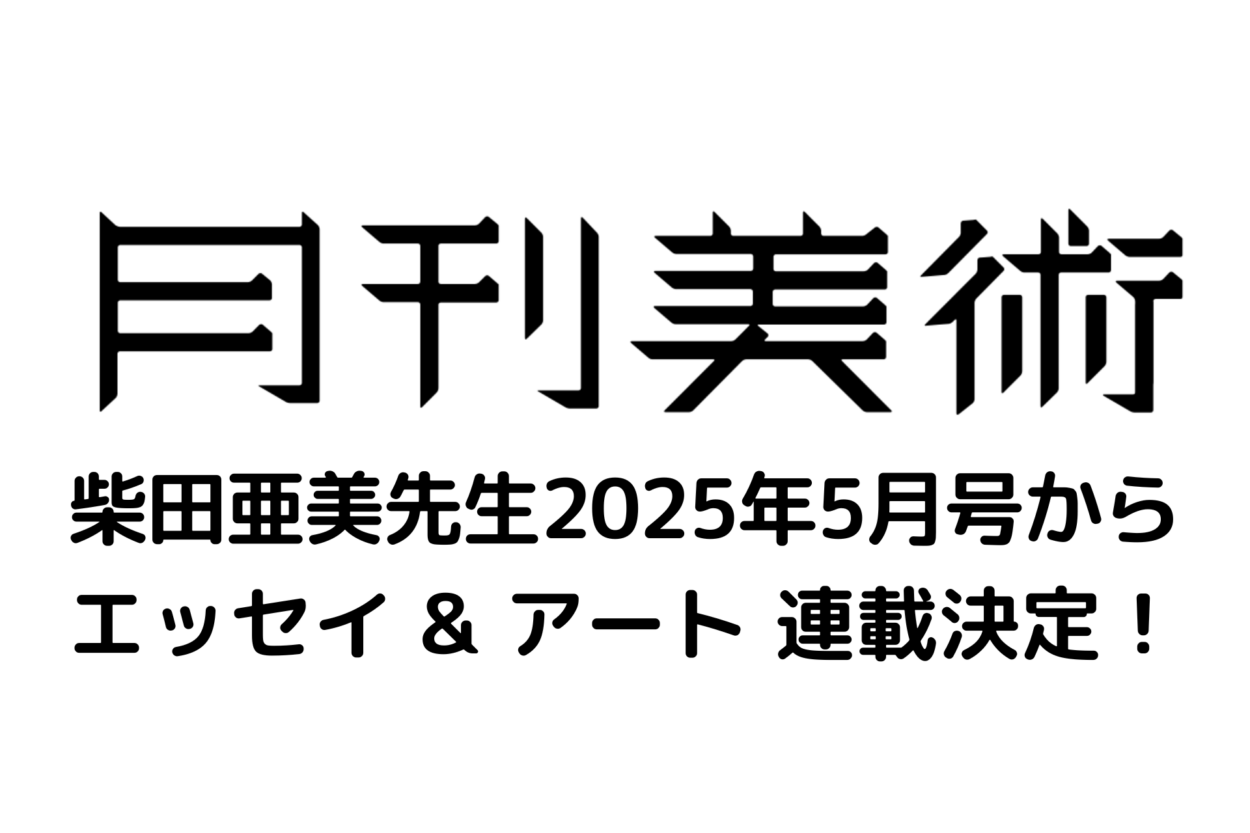西川美和(にしかわ・みわ)
1974年広島県生まれ。大学在学中に是枝裕和監督作『ワンダフルライフ』にスタッフとして参加。撮影現場での助監督経験の後、2002年『蛇イチゴ』でオリジナル脚本・監督デビュー。06年公開の『ゆれる』で注目を集め、09年公開の『ディア・ドクター』では、二度目のブルーリボン賞監督賞、芸術選奨文部科学大臣新人賞をはじめ多くの賞を受賞。12年『夢売るふたり』が公開。名実ともに日本映画界を代表する監督のひとりとなる。著書に、書評集『名作はいつもアイマイ』、小説では『ゆれる』(三島由紀夫賞候補)、『きのうの神さま』(直木三十五賞候補)、『その日東京駅五時二十五分発』がある。

Blu-ray&DVD『夢売るふたり』
監督・西川美和
(発売・販売元 バンダイビジュアル)
© 2012「夢売るふたり」製作委員会

長編最新作『夢売るふたり』Blu-ray&DVDと初エッセイ集『映画にまつわるXについて』発売!! 西川美和監督インタビュー
2013.04.18
『夢売るふたり』は、松たか子と阿部サダヲ演じる夫婦が、火事によって営んでいた居酒屋を失い、生きる糧として結婚詐欺を働く物語。『蛇イチゴ』は家族の崩壊と再生への兆しを描き、『ゆれる』では兄弟の心理に迫り、『ディア・ドクター』では「本物とは何か」という根源的な問いを映画化した西川監督。過去作品同様に「嘘」や「ペテン」というモチーフは一貫しているが、今回は加害者「夫婦」と被害者「女性たち」の生き方や孤独を、その鋭い人間観察力であぶり出している。
どん詰まりの夫婦、かけがえのない愛
――この作品はどんなところから発想したんですか。
西川 映画を発生させるときって、それまで気になっていたことが複合的に重なり一つの流れになっていくんです。以前から、どうにもならない夫婦の話を書きたい、とは漠然と考えていました。恋愛途中の生き生きとしたプロセスよりも、朽ちゆく関係を描くほうが自分には向いてるなって(笑)。でも、夫婦は停滞関係であって、珍しい存在でもないから、起爆剤となる仕掛けがほしかった。奥さんが夫の不倫相手の女性に慰謝料を請求する話をどこかで聞いて、「旦那だって悪いのに、冗談じゃない」って思いつつ、慰謝料目的に夫婦が結婚詐欺を働いていたら面白いんじゃないかと。共同作業の一つとして犯罪をやらせたら物語が転がっていく気がしたんです。
――恐い発想ですね。
西川 だからこそ面白い。夫婦で詐欺行為を働くという設定自体は現実的ではないですが、純粋な愛情や恋愛の果てに、共同でやる仕事や目的を持っていることでお互いの必要性を感じていられたり、一緒に居る理由を保てているカップルは多いはずと思います。それが商売であったり、子供の存在であったりするわけですよね。そういうものに頼らない以上つながりようのなくなったような、そういう夫婦像が描ければと。
――夫婦にスポットを当てたのはなぜですか。
西川 やっぱり非常に不可思議なものだと思ってきたからだと思います。夫婦にしか分からない絆や他人には入り込めない世界は実に千差万別で独特のルールを持ち、一つ一つが宇宙のように果てしなく、独身の私から見たら、うらやましくもある。だから、描きたかったのは、夫婦のかけがえのない愛、それから憎、女性たちの生き方でもあるんです。
涙には逃げない女の複雑さを描く
――これまで男性を主人公に長編を撮り続けてきた監督ですが、本作では女性を中心に描かれていますね。
西川 男性を描くことに飽きたわけではないですよ。男性は常にユーモラスで、魅力的です。すぐにでもまた書きたいです。女性を主人公にするのは今回が初めてで、実際に書き進めるとキャラクターが機嫌を損ねるというか、非常に難しかったです。複数の女性が登場しますが、特に主人公の里子は。ヒステリックに内面を爆発させた途端に陳腐になってしまう。女を突っ込んで表現しようとした時、どうしても映画だと泣き叫び、わめき散らすというところに落ちてしまう。それしかないのか。そうすれば本当にカタルシスが得られるのか? と私自身は観客としてずっと疑問に思ってきたんです。そうではなくて、どうやったら里子の闇、持ってる厄介さが表現しきれるのかなって、悩みに悩んで、黙っていることが個性、物言わぬヒロインに行き着いたんです。でも、事実女の人って泣くんですよね、すぐ。泣くこと=逃げ場所みたいに。書き手としては、そこに逃げようとしたらダメだ、違う道を探すんだって葛藤の日々。今回に限っては、出来るだけ泣かせたくなかったんですよね。泣くことで物事をおさめようとしない女を描こうと。女の涙で思い出しましたが、『スジナシ』という笑福亭鶴瓶さんがゲストと即興芝居を繰り広げる深夜バラエティがあるんです。その人の力量が丸裸になってしまう恐い番組なんですが、恐ろしいほどのポテンシャルを発揮する人もいれば、行き詰まったときに泣きで落とす女優さんもいる。「あっ、この人、泣いた。これで芝居を閉めようとしてるんだ」って(笑)。ついつい涙が出ちゃう場合もあるけれど、女の人は涙が武器になることを本能的にわかってるんです。すぐに涙が出るというのは女性の壊れ物のようなナイーブさの証明であり、同時に、「壊れる」ことに対する心理的ハードルも男性に比べてずっと低い。何度でも壊れるし、どこかでそんなこと屁とも思っていない部分もありますよ。壊してみせることすらあるし。それを含め、女はズルいしタフですね。厄介ですよ、男より。
女優・松たか子の得体の知れない魅力
――さすが鋭いご指摘。女は厄介という意味でも、騙しながらも申し訳なさがいっぱいの気弱な夫に比べ、平凡な妻・里子はモンスターのようになっていきます。その不気味さを、松たか子さんが『告白』(湊かなえ原作、中島哲也監督・脚本作品。松さんは教師役を怪演し、日本アカデミー賞優秀主演女優賞受賞)超えの恐怖演技で見事に体現されていました。
西川 松さんってサラブレッドなのに、いい意味で、佇まいは普通っぽい。築年数40年以上の安普請のマンションに住んでいる市井の人々のドラマを描く上で適役だった。しかも、特段悪人気質でもない、ごく一般的な善良な市民として生きてきた人が何でこんなことになったのか、段々グロテスクな展開になっていくので、松さんの押し付けがましくない“品”が必要だったんです。
――松さんは宛て書き(役者に合わせて脚本を書くこと)ですか。
西川 いいえ。香川照之さんに相談したんです、誰かいませんか、粋のいいのがって(笑)。香川さんは「俺に任せて。芸能界のウィキペディアだから」とおっしゃって、『告白』を薦めてくださいました。「松さんが凄くいい、あの人が抱えてる謎や闇、未知の部分は深い。得体の知れないものを感じるよ」って。急いで見てみたら、なるほど、この人は悪役が似合うなと。今回も、本人に罪悪感があるのかないのか、それすらもつかめない。その人がやってることが本当は正しいのかなって錯覚すらしてしまう。その曖昧な感じを出せたのは、松さんのキョトンとした様子、エグミのなさがあったから。松さんのおかげで、ああ、里子ってこんな感じなのかなって思いました。
――松さんの女優としての魅力はどんな部分でしょうか。
西川 不思議なことに、脚本の解釈や役作りに対して聞き返されたことも、意見を言われたことも一切ないんです。女優としての嗅覚がバツグンなんでしょうね。無色透明になって作り手に委ね、周囲をよく観察し、そこに自身の人生経験を織り交ぜ、的確に演じる。小さなこだわりは沢山あると思いますが、それを決して見せようとしない、徹底的なプロフェッショナル。生活感丸出しの、あえてダサいTシャツを衣裳に選んでも、「はい、分かりました」って、パッと着て、パッと試着室から出てくる。そういう時に、ことごとく、「こんなの(女としては)着たくない」とか「いっそもっとダサいのを着て、(女優として)かましてやりたい」とか、そういう「己(おのれ)」を微塵も出してこないんですね。プロであると同時に、すべてをこちらに委ねられる恐ろしさもある。一人の女性としてもステキな方だし、一緒にお仕事させていただいて、すごく好きになりました。
――被害者の一人、ソープ譲を演じた安藤玉恵さんも素晴らしかった。『ゆれる』でも書記官役で出演されて、西川作品常連の女優さんですね。
西川 ありがとうございます。以前「ジェイ・ノベル」の連載「映画にまつわるXについて」でも書かせていただいたんですが、吉原のソープランドに水着一丁で、夜中にフラッと取材について来てくれて。なかなか今日日ここまでやってくれる女優さんっていないよなと改めて思いました。安藤さんは、一緒に自主制作映画を作っているような感覚で接することができる唯一の女優さん。顔色を窺わずに気軽になんでも相談できて、男の俳優さんに近い雰囲気かな。思い切りの良さも含め、安藤さんなら体当たりでやってくれるだろうという算段もあり、今回は安藤さんだけは宛て書きでした。
カモにされる女性たちの多彩な職業
――ソープ嬢以外にも、カモにされる女性は普通のOLからウエイトリフィングの選手、シングルマザーの公務員と様々な職種の人が登場します。
西川 取材にはかなりの時間をかけ、普段あまりスポットライトの当たらないような職業の人を出してみようと。例えば、スポーツ選手だったら、今まで日本のスクリーンで見たことのない、マスコミに注目もされていない、日陰に咲くスポーツで、どんなものが面白いだろうと。たどり着いたのが重量級のウエイトリフィティング。実際に選手にお会いしたら、とにかく明るく魅力的で、そのひたむきさは映画のキャラクターに反映させてます。風俗嬢の「今は幸せ」っていうのも取材から得た本当の話。一般の女の人から見て最も遠い仕事かもしれないけど、会って喋ってみると、あんまり壁は感じなかった。やむにやまれぬ事情や、世を忍んで生きて行かなければならない辛さを抱えている一方で、自分の生き方よりもよほど豊かだと感じるところも少なくはなく、こういう生き方があるということを女たちに紹介したかった。男性を受け入れる懐の深さは、煩悩の多い娑婆の女に比べると神々しくさえ感じますし、まさに観音様ですよ(笑)。まだまだ自分の知らない女の世界がいっぱいあって、楽しかったですね。
――他にも気になる職業はありましたか。
西川 今回は抜け落ちちゃいましたが、電車の運転士さんとか。最前車両の小窓から見ていると、一人で薄暗いボックスの中で運転してらっしゃる後ろ姿や、終電後のホームを颯爽と歩く姿はステキだなって思いつつも、孤独だろうな、男の人と出会ったりするのかなって。あんな女の人の孤独が書けたら面白そうだと思ったわけです。
――結婚詐欺に関するリサーチはどのように行ったんですか。
西川 被害者の方にお話を聞いたり、探偵業の方に結婚詐欺に関するビデオを見せてもらったり。それが、加害者と被害者のご対面映像で、鬼の形相の女が男に殴りかかろうとしている修羅場。さらに、母親まで加わって男はボコボコ。女って、男に裏切られるとこんなになるんだなと思いました(笑)。まあ、自分の人生、全否定ですからね。殺したいほど腹も立つんでしょう。
影響を受けた、女性の描かれた小説
――女性を描くにあたって、これまでに読んだ小説の中で、影響や刺激を受けた作品を教えてください。
西川 パッと思いついたのが、ベルギーの作家シャルル・プリニエの『醜女の日記』。容貌の恵まれない女性の独白調の小説なんですが、たとえ愛されていても、常に疑心暗鬼。女性と容貌、それに対するコンプレックスって女性にとって根深い永遠のテーマ。男にとってはとるに足らないことかもしれないけれど、すべての女性にとって無視しえない問題です。そういう部分がよく書かれていた小説だと記憶してます。あとは有吉佐和子さんの『悪女について』。とんでもなく悪いことをした女の人について、関わった人たちの証言でまとめられています。面白いのは、人によって彼女の人物像が違うこと。悪く言う人もいれば、事件を起こすなんてありえないって言う人もいる。読めば読むほど、その女の実態がわからなくなり、どれも本当なんだろうな、これが人間だ、なんてしみじみ感じた小説です。
――他にもありますか。
西川 太宰治の短編『千代女』、女子中学生の一人称の話です。彼女が小学生の時に、文筆家の端くれみたいな親戚のおじさんに作文書いて懸賞に出してみろと言われ、それがたまたま評価されてしまったせいで、自分はそんなつもりはないのに、チヤホヤされて居心地が悪い。でも、いざ書こうと思った時には書けないという。「女性らしい作品」ではないかもしれませんが、モノを書いている身としては、この恐さはわかるんです。太宰は人間のコンプレックスを書くのは本当にうまいですね。ちなみに今挙げたタイトルに全部、女がついていますよ。
――センスを感じます。ところで、西川監督と言えば、心理描写のディテールへのこだわりに定評があります。しかも饒舌に語るのではなく、画やセリフの間で見せるという。今回も夫婦の感情の移り変わりを、二人の会話や視線で匂わせるとか、わずかなニュアンスの違いで描いてみせます。あの独特のうすら寒い会話や気まずい雰囲気は、体験者じゃないと出せないものだと思うんですが。
西川 私がそのシチュエーションを経験しているかはわからないですけど、気まずい雰囲気を描くのは自信があります(笑)。気まずいのって恐いですよね。だから、敏感ですよ、気まずさには。ボウリングでガターを連続する上司が振り返ったときの顔を見たら、どうリアクションをとったらいいのか。カラオケで選曲したもののサビしか歌えない人の顔を直視していいのか。人の「恥ずかしい」という感情に過敏なんです。そんな場面にあまり遭遇したくなくて、ボウリングにもカラオケにも行かないようにしているんです(笑)。まあ、物語のネタとして拝借する場合はあるかもしれませんが。
――今回、新たにチャレンジしたことはありますか。
西川 フィルムでなく、デジタル撮影をしたこと。たくさんの女優さんと仕事をしたということなどありますけれど、わかりやすいところだと、火ですね。水の表現に関しては『ゆれる』などで散々描いてきたので、火を起したらどういうドラマ展開になるんだろうという衝動にかられて。でも、居酒屋の火災のシーンは死と隣り合わせだったので、実際は大変でしたね。あと、東京の風景を撮るのも新たな試みの一つでした。浅草や中野などいろんなところでロケをして、東京に住んだことのある人が、なんとなく見たことのある風景を映せればと。
ラストをどう解釈するかに、その人の人間観が反映される
――夫婦関係はじめ、加害者、被害者、いろんな視点で楽しめる作品。エンディングの解釈も含め、何度でも繰り返し見たくなりました。
西川 うれしいです。騙す側を描くはずが、取材をするうちに、騙される側の人間臭さも描きたくなって、欲張っちゃいました。エンディングに関しては、悪人の話に違いはないので、作り手である私の意志として制裁を下さないと観客は納得しないのではないか、ふたりは幸せに暮らしましたとさ、では済まされないんじゃないかと、何パターンも悩みましたね。ただ、里子という人の生きる力、「生き欲」みたいなのものは強烈に残したかった。いずれにせよ、人間観や人間関係観、どう生きたいか、何を望むかで、解釈も違ってくるかと。そこはご覧になった方々の判断に委ねます。
――『ディア・ドクター』撮影後に、監督というポジションに居心地の悪さがあるとおっしゃっていましたが、少しは解消されましたか。
西川 居心地の悪さは常にあるし、自分に天賦の才能があってここのポジションにいるんじゃないって気持ちは一生変わらないだろうし。でもそれはもうそういうものなんだろう、丸ごと受け止めて行くしかないんだろう、という理解と締念に行き着いたようにも思います。『ディア・ドクター』で、偽者が偽者ゆえの葛藤を抱える物語を書けたことで消化された部分もある。見てくださった一般の方々の感想を聞くことで、自分だけじゃなく、多くの人が居心地の悪さを抱えながら自分に与えられた仕事と向き合ってるんだとわかったことも大きかったですね。
――腹をくくったという。
西川 そうですね。でも、いつでも辞められるというか、しがみついてまでやらなきゃいけない使命みたいなものは私の中にはなく……。ただ、毎回、これがラストだなって思いながら撮ってます。
――最後に、この作品を経て夫婦関係や、女性という生き物に関して改めて思うことはありますか。
西川 夫婦は厄介なり。その反面、夫婦って凄くいいと思う。他人同士が夫婦になれることが、かけがえのないことだと思うし、夫婦でい続けられることって素晴らしい。松さんと阿部さん、現場にいるふたりの佇まいも目を細めたくなるほど温かくて。私もチャンスがあれば結婚生活にトライしてみたいなと。女性もまた、厄介なり。そして可愛いですよね。どこまでも。
※本インタビューは、『夢売るふたり』公開に合わせ、小説誌「月刊ジェイ・ノベル」2012年9月号に掲載したものです。
※エッセイ集『映画にまつわるXについて』は、同名連載の11回分の原稿を中心に、新聞や雑誌、ウェブなどで発表されたものをまとめています。